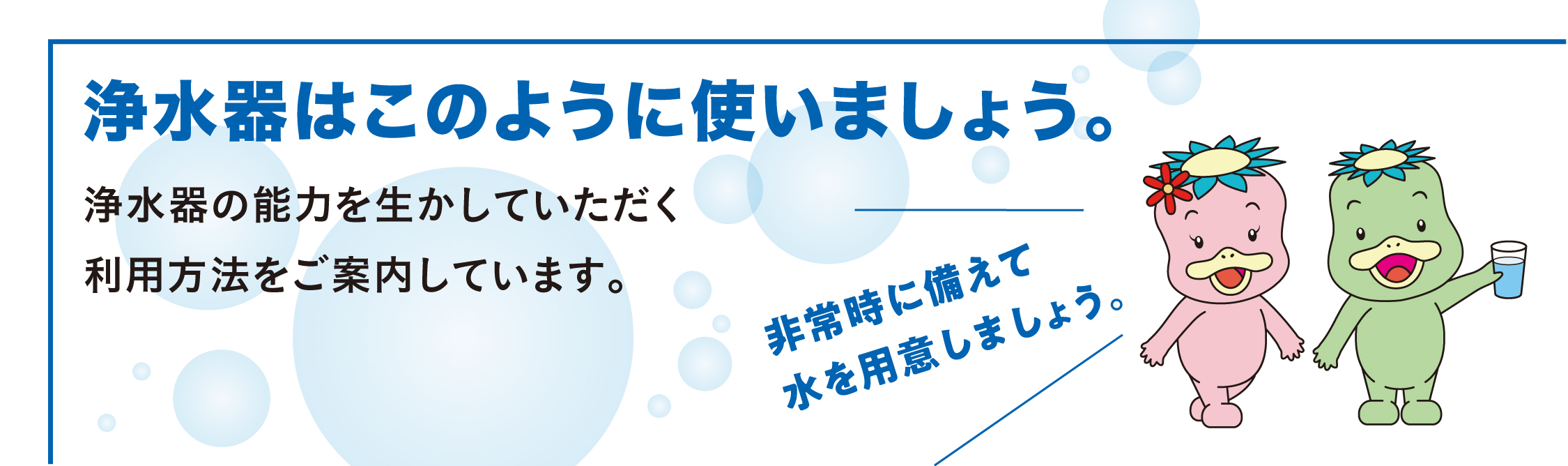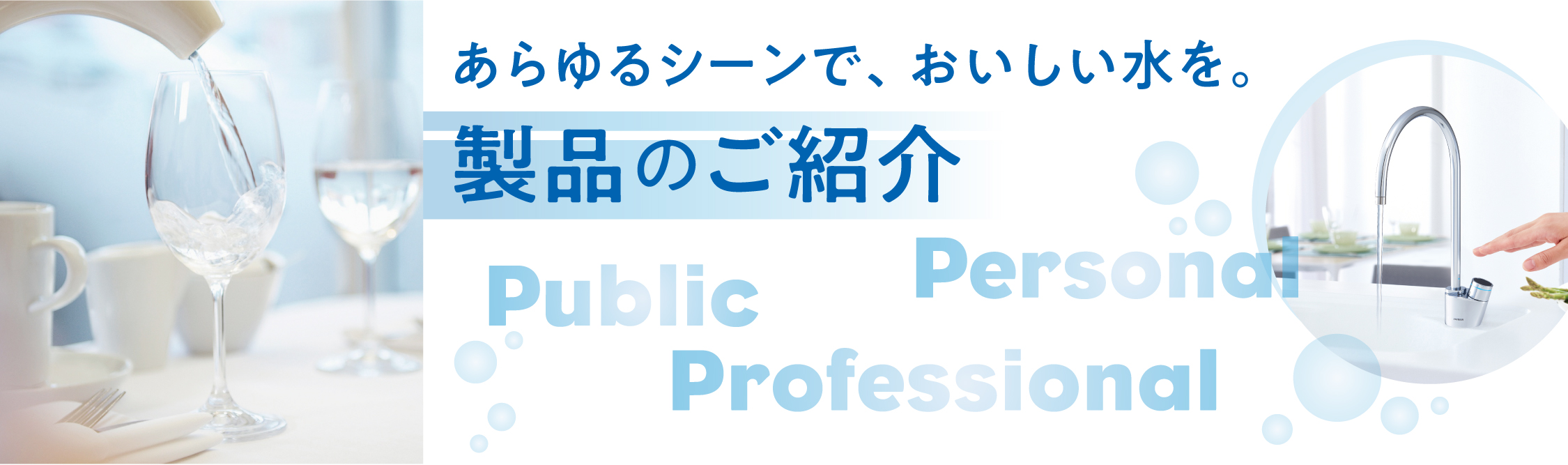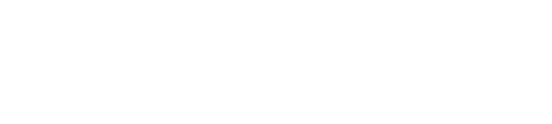めいすいの里山便り
四季折々の命
毎年リポートしていただいている「めいすいの里山」の様子。年を追うごとにさまざまな動植物や昆虫が豊かな営みを取り戻しているのを感じます。2024年の里山はどうだったのでしょうか。今年も今森光彦さんに振り返っていただきました。
寄稿 今森光彦 写真 今森元希

春

春の野面(のづら)は、思わず駆け出したくなる

タニウツギは豪華な花を咲かせる。
温かい空気に触れると心がウキウキしてきます。土手や道脇の草はみずみずしく、寝転びたくなるくらいに気持ちがいいのです。目線を低くすると、いろいろな生きものに出会えます。細長い触手を伸ばすカラスノエンドウの小さな葉にナナホシテントウがとまっていたりします。タンポポやナズナなど、背丈が低い春の花もいっぱい咲いています。一日が終わってほしくない――春ならではの願いごとです。
夏

斜面はハサミを使って草刈りをする。

ヤマボウシの花は清楚で美しい。
木々の葉が鬱蒼(うっそう)と茂る夏。セミの声は、初夏のニイニイゼミから盛夏を告げるアブラゼミの歌声へと変わってゆきます。「めいすいの里山」では、一年の中でもっともつらい夏の草刈りが待っています。でも、汗を流した後の休憩はなんとも心が癒やされます。一方、生きものが大好きな人は、一瞬たりとも目が離せないほどのいそがしさになります。夏は、好奇心旺盛な人は童心に返る季節でもあります。
秋

ときどき散策会をして季節を楽しむ。

秋の土手に自生するリンドウ。
ヤマモミジの葉が赤く色づきました。これらの木は植栽したもので、だいぶ大きくなりました。クヌギは黄葉(こうよう)するので山全体が明るくなったように感じます。「めいすいの里山」ではこの気持ちが良い季節に、木々の世話はほどほどにして散策会を開催することがあります。木の実を探したり秋の野草を観察したり。植物たちの色づきはとても豊か。里山の植物の種類の多さを実感するときでもあります。
冬

ため池と湿地を結ぶ側溝を掃除する。

冬に鮮やかな花を咲かせるヤブツバキ。
冬の「めいすいの里山」には、田園から清らかな風が吹いてきます。枯野の中でいろいろな生きものが冬越しをしていることを考えるとうれしくなってきます。大倉川の近くにはヤブツバキがたくさんあって鮮やかな花を咲かせます。よく観察しているとヒヨドリやメジロがひっきりなしにやって来て蜜を吸っています。冬の里山管理では、木の枝打ちや溝掃除など、春に向けて怠ってはならない大切な作業を行います。