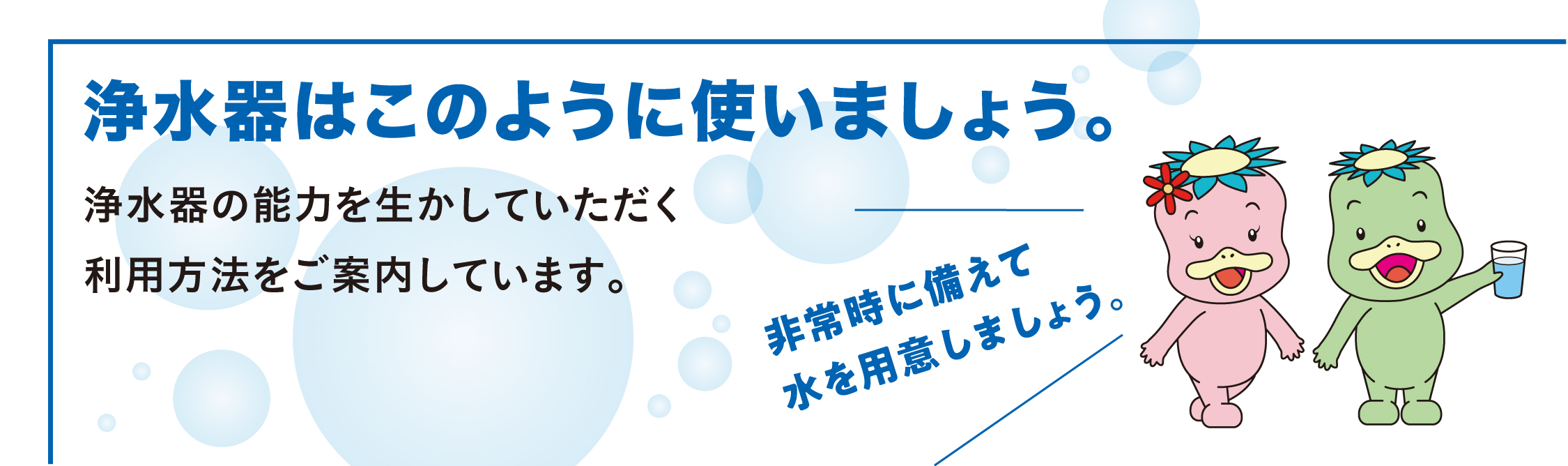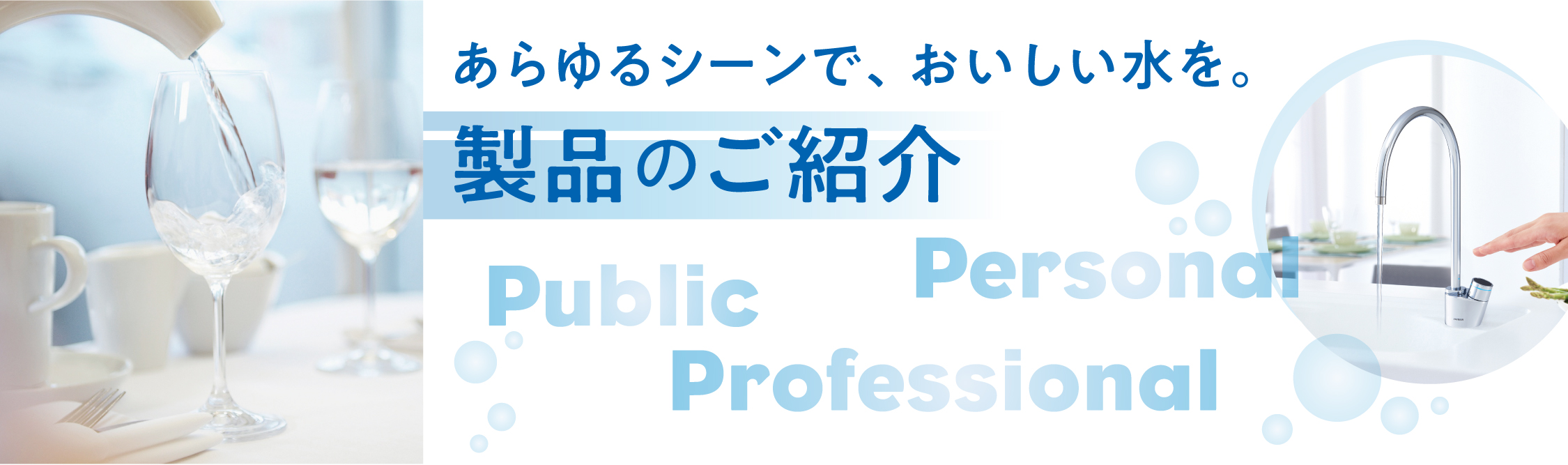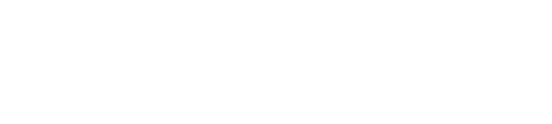井澤由美子の食文化探訪 Vol. 1「酢」とレシピ
日本の食文化を追い求めて料理家の井澤由美子さんが旅する「食文化探訪」。その1回目は日本の発酵食品の一つである「酢」に注目し、1711年に酢造りをはじめた醸造所を訪れ、伝統のある酢造りと「酢酸菌」を取材しました。
酢
醸造酢は穀物や果実などを原材料とした酒を発酵させて造られる。日本ではJAS規格(日本農林規格)によって、酢は醸造酢と合成酢に分けられ、醸造酢は原料によってさらに穀物酢、果実酢、醸造酢の3種類に分かれている。醸造酢によって造り方や保蔵菌が違うため蔵の数だけ味があるといわれる。

伝統的な発酵技術で造られる酢
現在、流通する酢はろ過や殺菌を経た透明な状態のものも多いですが、自然の力をそのまま詰めた「にごり酢」という酢があります。
福岡県大川市は、筑後川の豊かな水の恵みを受けて、古くから米どころとして栄えてきました。今回訪れた「庄分酢(しょうぶんす)」は、1624年にこの地で造り酒屋を創業し、1711年に酢造りをはじめた醸造所です。300年もの間、蔵に棲む酢酸菌を大切に育みながら独特の酸味をもつ酢を生み出してきました。
「当社では“くろ酢(す)”が主力です。手間暇かけて甕(かめ)で発酵させています。酢造りに欠かせない酢酸菌は、体によい効果があることが分かっています。にごり酢は昔から自然のままに活用していた菌の力をそのまま詰めています」と15代目当主の高橋清太朗(たかはしせいたろう)さんが教えてくれました。
日差しや雨から酢を守るために建てられた酢の蔵。中には、酢酸菌が入った大きな黒い甕があり、その和紙のふたを開けると、「しっかりと膜が張られ、菌たちが生きているのがわかりますね」と井澤由美子さん。玄米の香り、酒の香り、酢の香りの三つが入り混じった甕をうれしそうにのぞきこみました。
「最初にお酒の発酵が進んで炭酸ガスがボコボコと発生し、お米も液面にまで上がってきます。お酒の発酵が終わり落ちついてくると膜が張ってきます。酢酸菌が膜を作りその中で活発に活動しておいしい酢が造られていきます」と高橋さん。

「いつ開けたのか、仕込んだのはいつなのかがわかるように縄の結び方がそれぞれ違います」という甕の和紙のふたを開けると、ほわっと温かな空気が流れ出し、菌が生きていることを感じる。
次に真っ黒になった木壁に覆われた土蔵に入っていくと、日本では珍しくなった酢造り用の木樽が並び、食酢が造られていました。「甕だけでなく木樽にも素敵な菌が棲んでいるんですよね!」と言う井澤さんに、「生きた酢酸菌は、木の表面や内側のでこぼこの中に棲みついているので、つるんとしたステンレス樽などよりも昔ながらの道具のほうが菌にも居心地がいいのかなと思います。冬には菌が過ごしやすいようにムシロをかけて温かくしたりするんですよ」と高橋さん。

たくさんの木樽が並ぶ土蔵の醸造所。木樽作りの職人が減りメンテナンスも難しくなってきたため、国内の醸造所が連帯して技術の継承を目指しているそうだ。土壁を利用し続けるのは大切な菌が棲息しやすいようにするため。取材にご協力くださった庄分酢の常務取締役で15代目の高橋清太朗さん(左)と、井澤由美子さん(右)。

井澤さんも感嘆した「素敵な黒い木壁!」の歴史ある蔵。菌が木壁について黒く変化したもので、菌を大切にしてきた証しでもある。
発酵食品である酢には抗菌作用があり、胃腸を整えてくれ、うま味成分であるアミノ酸が多く含まれています。井澤さんは、「なかでもにごり酢は、酢酸菌がたっぷり入っています。海外では酢酸菌はマザーとも呼ばれていて、免疫力を高めてアレルギー症状を抑制するなど体にうれしい効果が期待できます。酢ならではの生きた菌の力を日々の生活に取り入れて、おいしい食事を作っていきたいですね」と酢への思いを語りました。

庄分酢の本店の建物は大川市の指定文化財にもなっている。250年の歴史をもつ町屋造りの建物の1階はビネガーショップ。

庄分酢の『蔵付酢酸菌 かすみくろ酢』。黒酢(くろず)だが、この酢は日を当てていないので色が茶褐色でないという。

2階には酢を使ったフルコースのランチがいただけるレストラン「リストランテSHOUBUN」がある。
庄分酢
住所:福岡県大川市榎津548-1
お問い合わせ・予約:0944-88-1535(お電話での問い合わせは9:00~17:00)
営業時間ほか、詳しくはウェブサイトをご参照ください。