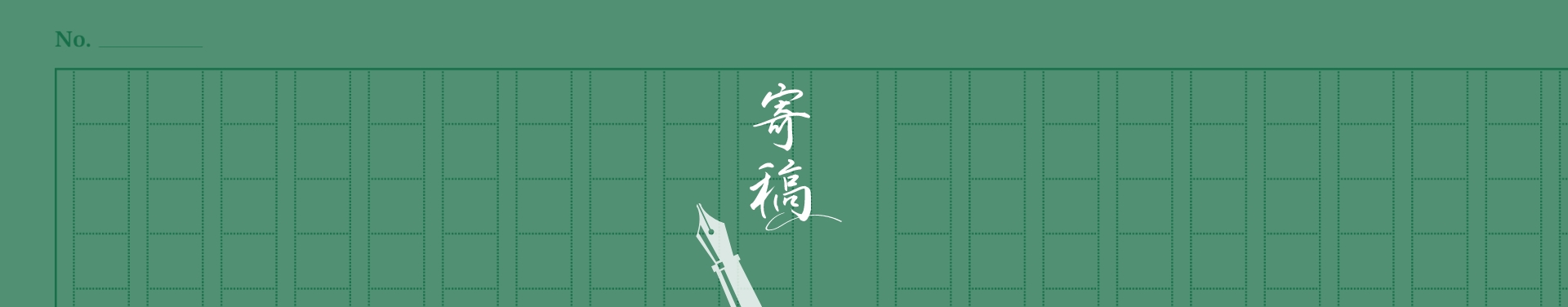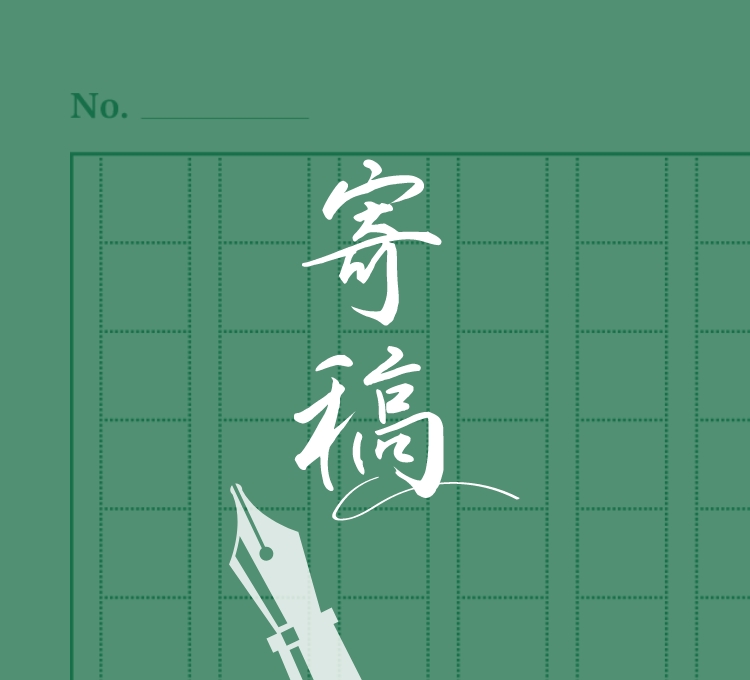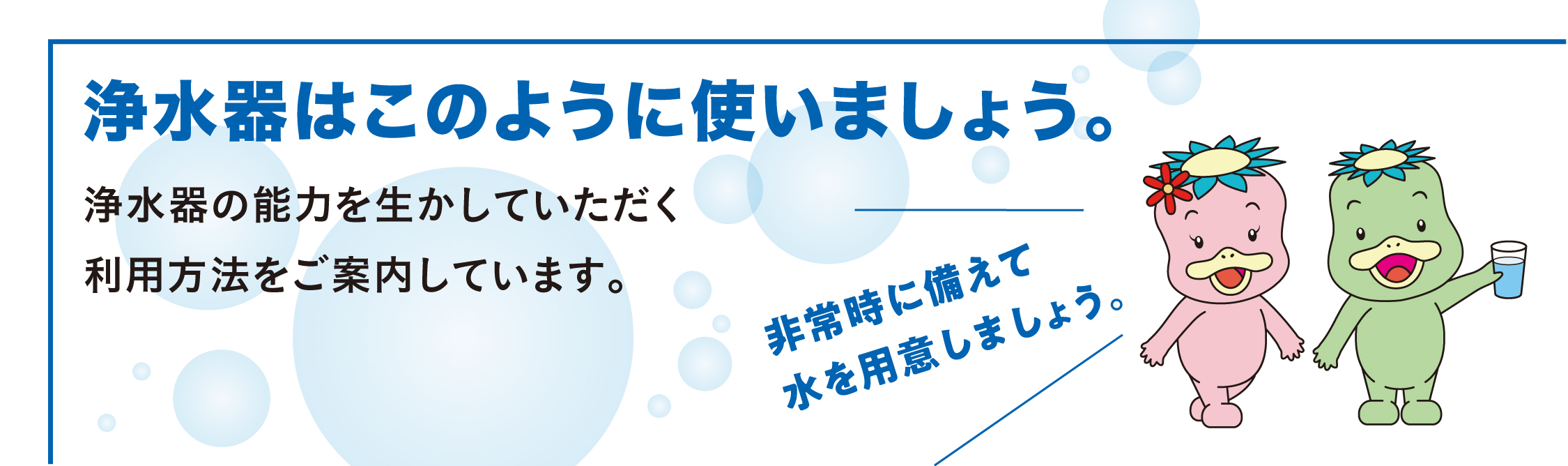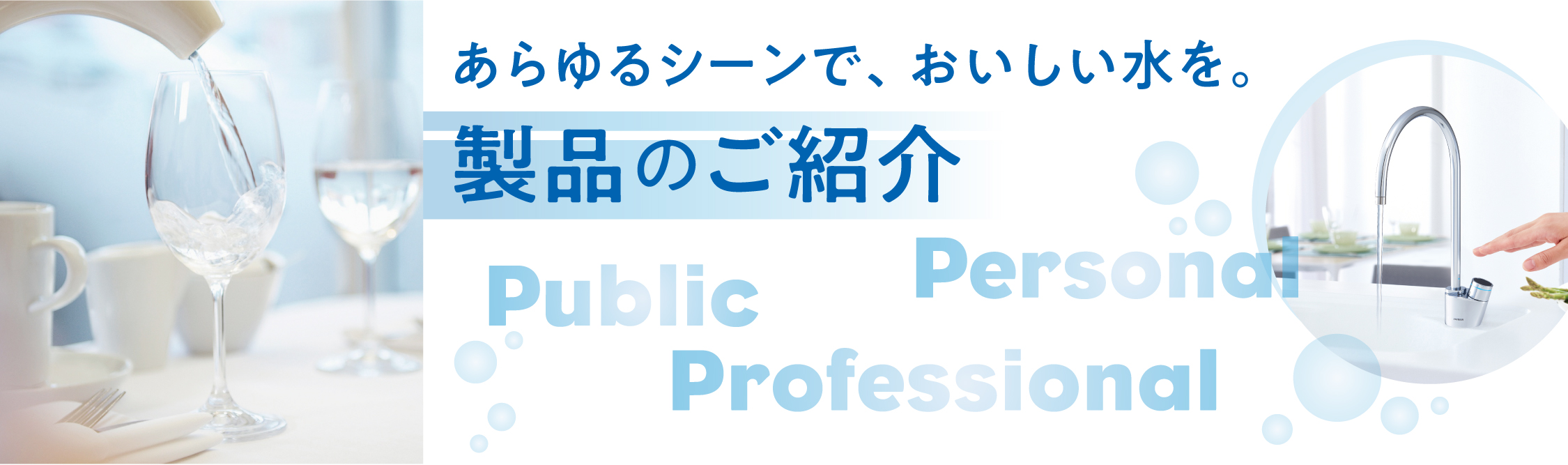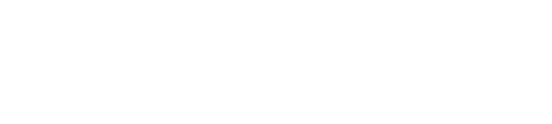水は生命の媒体
寄稿 福岡伸一
生物学者・作家
福岡ハカセが〝日本が水の国であることを感じさせてくれるすばらしい風景〟を訪れて、自然と生命、そして水の大循環に想いを馳せました。

静岡県の柿田川(かきたがわ)湧水地を訪れた。富士山に降った雨水が数十年もかけろ過されてこの場所に湧き出た景勝地で、日本三大清流、日本百名水にも選ばれている(三大清流は柿田川のほかは四万十川(しまんとがわ)と長良川(ながらがわ))。水源に行ってみると深い井戸の青い底から清らかな水がこんこんと湧き出していた。湧水場所は何か所もあり、一日に全部で100トン以上もの水量があるという。水はこのまま柿田川となって流れ出し、あたりは自然公園として整備されている。遊歩道に沿って歩くと、川岸は豊かな広葉樹林に囲まれ、水辺には小さなカニ、淀よどみには小魚が群れている。私の好きな昆虫類も豊富だ。チョウが舞い飛び、トンボ類もたくさん飛び交っている。見つけることはかなわなかったが、この場所にしか生息しない希少種アオハダトンボもいる。この水は、静岡県東部住民の飲料水源にもなっている。柿田川は下流で狩野川(かのがわ)と合流し駿河湾に出る。あらためて日本が水の国であることを感じさせてくれる、すばらしい風景だった。
遠くに富士山の秀麗な姿を見ながら地球の水の循環のことを考えた。川から海に注いだ水は、太陽の熱によって温められ、塩分を海に残して蒸発していく。上空に昇った水蒸気は今度は冷やされ、雲や雨滴、または雪になる。それらは大地に降り注ぐ。降ったおおくの水はどこかの段階で一度は生命体の中を通過する。森林に降った雨は植物体の中へ、土壌に降った雨は土壌微生物の中へ、海水の水は海洋生物の中へ、飲料水となった水は私たちの身体の中を通る。
植物にとって水は光合成に必須の材料である。空気中から吸収した二酸化炭素の炭素とともに有機物の構成成分となる。植物は利他的に振る舞う。過剰なまでに光合成を行って、葉っぱを茂らせ実や穀物を作り他の生物の食料として与えてくれるからだ。もし植物が利己的に振る舞って自分に必要なだけしか光合成をしなければ他の生物が生存する余地はなかった。
動物にとって水は生命の媒体だ。細胞内外のあらゆる化学反応は水の中で起きる。水がないとタンパク質もDNAも合成できない。さらに水がないとタンパク質もDNAも分解できない。そして水は酸素を含んで身体の隅々に運び、二酸化炭素や老廃物を溶かして身体の外に運び出す。人間が飲んだ水は、老廃物を運び出すためにおよそ数時間のうちに体外に出される。それは呼気、汗、尿、便などとともに排出される。冬場、寒くなるとトイレが近くなるのは、汗で排出しにくくなる水分が尿に回るからである。
それゆえ私たちは生きるためにきれいな水を飲まなければならない。きれいな水とは、細菌や有機物に汚染されていない水で、生命に必要なミネラルを適量含んだ水ということである。

福岡伸一 FUKUOKA Shin-Ichi
ふくおか・しんいち●生物学者・作家。京都大学卒業、同大学院博士課程修了。ハーバード大学研修員、京都大学助教授などを経て、現在、青山学院大学教授、米国ロックフェラー大学客員教授。サントリー学芸賞を受賞して90万部のロングセラーとなった『生物と無生物のあいだ』や『動的平衡』シリーズなど、“生命とは何か”を動的平衡論から問い直した著作を数多く発表。他に『世界は分けてもわからない』『できそこないの男たち』、朝日新聞の連載をまとめた『ドリトル先生ガラパゴスを救う』など。『週刊文春』『アエラ』『婦人之友』に定期寄稿。大阪・関西万博(EXPO2025)テーマ事業館「いのち動的平衡館」プロデューサーを務める。